食を通じた村民交流「第11回おやきを食べる会」を、24日に小川村公民館で開催しました。今回のテーマは”地粉でタコス!”村の小中学校で英語講師として指導されているアン先生に紹介役をお願いして、みんなで地粉を練ってメキシコ料理のタコスを作りました。元々メキシコ料理のタコスですが、最近はアメリカでもポピュラーなエスニック料理になってるんですね。具材には、タコミート(スパイシーな肉ミンチ)、グアカモレ(アボカドサラダ)、ピコデガヨ(トマトと玉ねぎのライム和え)を準備、地粉で作った皮も絶妙で、美味しくいただきました。ご指導いただいたアン先生ありがとうございました。
2019年2月25日月曜日
2018年6月6日水曜日
「西山大豆を活用した小川村・地域活性の取り組み」が月刊誌「信州自治研」に掲載されました
my report about our soy-bean project in Ogawa has been published
長野県地方自治研究センターで発行している「信州自治研」という月刊誌の最新号(6月号)に、だいずの楽校長が寄稿した「西山大豆を活用した小川村・地域活性の取り組み」が掲載されています。どこかで冊子をとる機会がありましたら、ぜひご一読ください。
※寄稿文の本文データ(ワードファイル)をお分けすることもできますので、ご興味ある方はご連絡下さい~(と、添付の写真を見れば、全文が読めるような・・・。マラウイ時代の懐かしい写真も使わせてもらいました)
2018年5月30日水曜日
第7回 おやきを食べる会「卯の花」&「野草(セリ、アザミ)」のおやき
held a Oyaki cooking party@ local health center


第七回おやきを食べる会を30日開催しました。今回のテーマは「卯の花」と「野草(セリ、アザミ)」のおやき。小麦粉と大豆はパチョコ農園産、野草は我が家の畑で採ったものと、参加したみなさんが提供してくれました。


搾ったばかりのオカラで作った卯の花も良かったのですが、パンチ力があったのは野草のオヤキ!アザミもセリも個性強くて面白いですね。これぞ、季節と大地を感じるおやきの醍醐味。

即興で作ったオカラ茶と湯葉もまあまあ好評だったので、次回のだいずの楽校で使えそうです。
毎度毎度ご協力いただいている食生活改善推進協議会のみなさん、ありがとうございました!

ちなみにテレビ信州さんが取材にきていました。

11月?頃に放送されるかも。 次回のおやきを食べる会は、パン作りの予定です。




第七回おやきを食べる会を30日開催しました。今回のテーマは「卯の花」と「野草(セリ、アザミ)」のおやき。小麦粉と大豆はパチョコ農園産、野草は我が家の畑で採ったものと、参加したみなさんが提供してくれました。


搾ったばかりのオカラで作った卯の花も良かったのですが、パンチ力があったのは野草のオヤキ!アザミもセリも個性強くて面白いですね。これぞ、季節と大地を感じるおやきの醍醐味。

即興で作ったオカラ茶と湯葉もまあまあ好評だったので、次回のだいずの楽校で使えそうです。
毎度毎度ご協力いただいている食生活改善推進協議会のみなさん、ありがとうございました!

ちなみにテレビ信州さんが取材にきていました。

11月?頃に放送されるかも。 次回のおやきを食べる会は、パン作りの予定です。


2018年3月6日火曜日
西山大豆フェアで「だいずニャマ」完売!
2018年3月2日金曜日
アフリカ生まれの大豆フード 西山大豆フェアでデビュー!
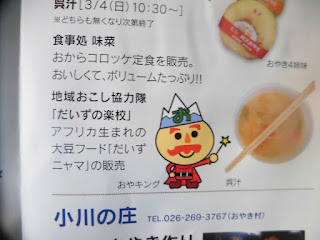
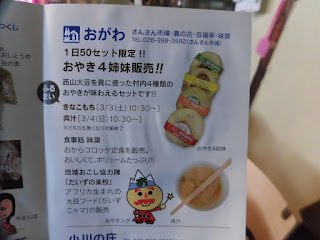
今週末の3日、4日、いよいよ西山大豆フェアです。今年は、マラウイ時代から長い付き合いになる大豆フード「だいずニャマ」を屋台販売する予定です。

だいずの楽校では、連日、磨り潰した大豆を使って、
「だいずニャマ」の試作を繰り返しています。
アフリカン向けだと、油たっぷり、カラッと揚げるのが良さそうですが
ヘルシー志向の日本人向けには、少々油控えめで行こうかと思います。


ファストフードです。
この味がどこまで一般受けするのか、少々不安もありますが、小川村でのデビューなので楽しみでもあります。10時~13時で販売しているので、ぜひ気軽に遊びに来てください。大豆でつなげるマラウイと小川村、記念すべき第一歩です!

2018年2月23日金曜日
小川小学校で豆腐作り(のお手伝い)
2018年1月22日月曜日
手打ちうどんと、おせちの残り物で創作オヤキの会
1月21日、村民交流会「第五回おやきを食べる会」を開催しました。老若男女あわせて約20人にご参加いただき、にぎやかに実施しました。
今回は「正月」らしく、手打ちうどんと、おせち料理の残り物を使ったおやきを作りました(小川村では、正月にうどんを食べる風習があるそうです)。
村のお母さん方に教えていただき、うどんもおやきも大成功!手打ちのうどんは腰があって、後をひく美味しさでした。サツマイモのきんとんを具にしたおやきも大評判。
みなさんに楽しんで交流していただけたようで、何よりでした。次は、何を作って食べようか、今から楽しみです。
2017年12月19日火曜日
横山タカ子さんから、たらこ入りだし巻き卵を習いました

かの著名な料理研究家、横山タカ子さんの料理教室が
小川村で開かれ、自分も参加してきました。
今回は、三度にわたるシリーズの最終回で、テーマは
「正月料理」。
肉巻きおにぎりとか、色々作ったのですが、とくに印象深いのは
たらこを中心に巻いたダシマキ卵、その名も「日出巻」!
断面を見ると、太陽のように見える目出度い料理です。
というわけで、ダシマキ卵を人生で初めて習いました。

味付けは、砂糖としょうゆのみ。化学調味料とは無縁で、
調味料がシンプルなのも横山流です。

焼く際のコツは、こまめに油をしっかり敷くことだそうです。
あとは、四角い専用のフライパンを使いなさいと。
できれば、銅がおすすめとのこと。8000円くらいするそうですが・・・
とりあえず、見よう見まねでやってみました!
出来栄えはこんな感じ。
なかなか良いのではないでしょうか。

包丁でスパッと切って、断面を見ると・・・
Oh! Sunrise!てな感じで、日出っぽい!

なかなか上手にできました。
他の料理はこんな感じ。

今後は、毎朝自分で卵焼きを焼こうと思います。
ということで、早速アマゾンで銅製のフライパンを注文してしまいました。
横山効果絶大です。
日本人らしい朝ごはん、がんばろ~
2017年10月30日月曜日
おからこんにゃく料理講座 開催しました!
「肉は一切使っていません」というときっと驚かれるような料理たち。本日は、だいずの楽校特別編として、青森県生まれのスーパーフードおからこんにゃくを使った料理講座を開催しました。
講師は青森県から奇遇にも来村していた、おからこんにゃくマイスターの有資格者を招きました。おからとこんにゃく(+長芋など)を合体させると、こんな食感になるというのは未経験の人にはビックリかもしれません。作ったのはハンバーグと鳥の照り焼きと海老団子スープ。動物性食材が一切含まれてないのに、見た目はまさしく、肉・肉・肉!
小川村の料理ベテランのみなさんが「本当に肉を食べてるみたい!」と驚いてました。カロリーも少なく、食物繊維豊富なので、現役の看護師さんからは「病院食にも良さそう」との感想をいただきました。
今回は試行企画でしたが、参加者のみなさんから自発的に「またやりたい」「おからこんにゃく自体も作りたい」との声があったので、シリーズ化しそうです。おからこんにゃく、なかなか面白いですよ~。
2017年8月24日木曜日
【だいずの楽校】牛乳パックで豆腐作り体験
2017年8月18日金曜日
松川村でケチャップ作りを習ってきました!

松川村まで遠征して、地元の女性グループからトマトケチャップ加工法を学んできました。丁度、地元の中学生に教える機会があると聞き、そこに混ぜてもらいました。今まで本を頼りに我流でやっていたので、学ぶこと多数。やはり先達に教えを乞うことは大事ですね。
機材を買いそろえる財力はありませんが、要点はつかめました。次のトマト加工日が楽しみ!

ちひろ美術館にほど近い農場。加工トマトは露地栽培です。

肥沃な火山灰土で、トマトの育ちも良いとか。わが畑と比べると、ずいぶん
トマトの色つやが違います・・・

トマトの芯をリンゴの芯抜き機で取り除きます。これは勉強になりました。

専用の機械で、湯煎したトマトをつぶして、ジュースと皮に分離します。
普段ジューサーで地道に作業している身としては、うらやましい!

出来上がったケチャップは、専用の漏斗のような機材で、パウチに
充填します。これも便利!5000円強で買えるそうです。
パウチにつめたケチャップは、大きなかごに入れて、丸ごと鍋に突っ込んで
熱湯殺菌します。85度で15分。

瓶のように、事前消毒する必要がないのでとても楽です。
が、再利用はできないため、コスト面では一長一短です。

長い歴史のある松川村のトマト加工に、いきなり追いつくことはできませんが、
小川村での加工においても参考にできる部分がありました。次回以降、少しずつ
採り入れて、小川村におけるトマト加工の質も高めていきたいものです。
登録:
投稿 (Atom)


























